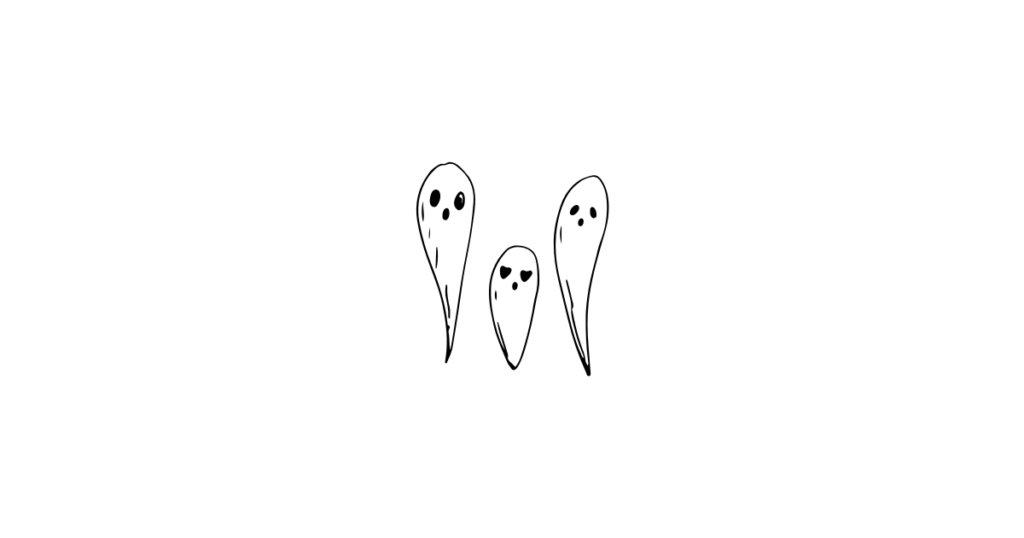
なぜ7月26日が“幽霊の日”?
この日は、1825年(文政8年)に江戸の中村座で、四世鶴屋南北作の歌舞伎『東海道四谷怪談』が初演された日。
そのため、7月26日は「幽霊の日」とされています。
四谷怪談といえば、お岩さんの怨霊で知られる日本の怪談の代表作。
この日をきっかけに、日本の“怪談文化”の奥深さに触れてみませんか?
幽霊が“夏の風物詩”になった理由とは?
実は、幽霊や怪談が夏に語られるようになったのには理由があります。
🌀 江戸時代、涼を取る手段が少なかった時代に、背筋がぞっとする話を聞いて涼を感じていたと言われています。
👘また、お盆やお彼岸など、先祖の霊を迎える季節とも重なり、自然と「霊=夏」のイメージが定着していきました。
👻 日本三大幽霊を知っていますか?
日本で特に有名な“幽霊三人衆”がこちら:
- お岩さん(四谷怪談)
- お菊さん(番町皿屋敷)
- お露さん(牡丹灯籠)
どれも裏切り、嫉妬、復讐、哀しみといった人間の感情が渦巻く物語。
だからこそ時代を越えて語り継がれているのかもしれません。
怪談の楽しみ方|“怖さ”だけじゃない、日本の情緒
最近では「怪談=怖い話」だけでなく、文学的・芸術的に楽しむ人も増えています。
📚 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の『怪談』や
📺 昭和の名作ホラー映画、
🎧 朗読アプリで聴ける怪談集など、
自宅でじっくり“涼”を感じられるコンテンツも充実。
🏠 おうちで楽しむ「怪談ナイト」アイデア
- 部屋を薄暗くしてキャンドルを灯す
- オーディオブックや怪談YouTubeを再生
- 扇風機+冷たいドリンクで涼を演出
- ちょっと怖い和菓子やお化けモチーフのお菓子もおすすめ
🎧【PR】朗読で楽しむ本格怪談!
👉 Amazon Audible(無料体験あり)で怪談を聴く
幽霊の日に“ちょっと怖くて、ちょっと涼しい”体験を
人間の心理や文化に深く結びついている怪談の世界。
「幽霊の日」は、単なるホラーではなく、日本の情緒や歴史を味わえる特別な日でもあります。
今年の夏、あなたも“背筋がぞくっ”とする時間を過ごしてみませんか?


