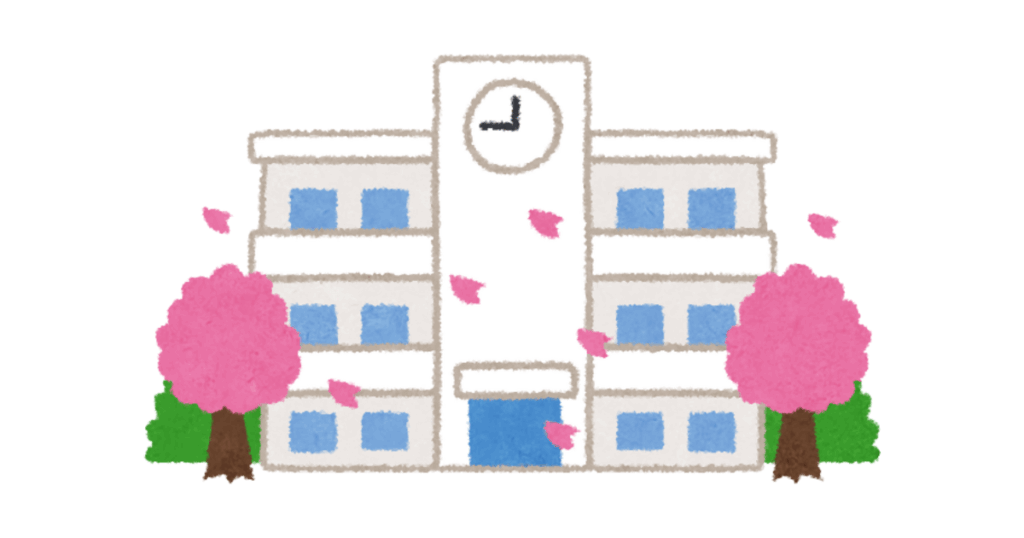
はじめに:5月21日は何の日?
明日5月21日は「小学校開校の日」。
普段、何気なく通っていた小学校にも深い歴史があることをご存じですか?
1872年、日本初の小学校が開校しました。
それは東京・築地に設立された「成徳学校」です。
当時の日本は近代化の真っ只中。
教育の普及は国を支える重要な施策として位置づけられました。
今回は、小学校の誕生背景や現代教育との違いについて解説します。
日本初の小学校の誕生とその背景
なぜ1872年に小学校が設立されたのか?
明治政府は「富国強兵」「文明開化」を掲げ、教育の普及を急務としました。
その一環として発布されたのが「学制」(がくせい)です。
「学制」とは、全国一律の教育制度のことで、6歳以上の子どもたちに初等教育を受けさせることが義務付けられました。
成徳学校の特徴:
- 開校日:1872年5月21日
- 場所:東京・築地
- 対象:6歳から14歳の男女
- 教材:石板、木板(紙は貴重品だったため)
- 授業内容:読み書きそろばん
成徳学校は、日本初の小学校として教育の礎を築きましたが、当時の授業内容は極めて基礎的なものでした。
義務教育の始まりと小学校の拡大
成徳学校の開校を皮切りに、全国で小学校の設立が進みました。
しかし、初期の段階では「学費」が障壁となり、貧困層の子どもたちは通えないことも。
学制発布後の教育の拡大:
- 1872年:学制発布
- 1886年:義務教育が4年間に短縮
- 1907年:義務教育が6年間に延長
- 1947年:義務教育が9年間に延長(現行制度の基盤)
このように、日本の義務教育制度は徐々に拡大し、教育の普及が進んでいきました。
現代の小学校と教育の進化
現代の小学校は当時の成徳学校とは大きく異なります。
ICT教育やリモート学習、プログラミング教育など、新たな学びの形が次々と導入されています。
現代教育の特徴:
- プログラミング教育の必修化(2020年〜)
- ICT機器の活用(タブレット、電子黒板)
- 環境教育やSDGsの取り組み
- インクルーシブ教育の推進
昔の「読み書きそろばん」に加え、現代では「情報リテラシー」や「デジタルスキル」が必須となっています。
おすすめの教育関連アイテム
明治時代の「読み書きそろばん」に代わり、現代の教育では デジタル教材や知育玩具 が学習サポートに役立ちます。
以下のアイテムは、成徳学校の授業と現代の学びの違いを体感できるアイテムです。
学習教材・知育玩具
- 学研の図鑑LIVE: 動画や写真で学べる図鑑。動物や宇宙など、興味に応じて選べます。 ➡️ https://amzn.to/431qAjd

- くもん出版のドリルシリーズ: 基礎学力を養うためのドリル。繰り返し学習で確実に力をつけることができます。 ➡️ https://amzn.to/4km23eo
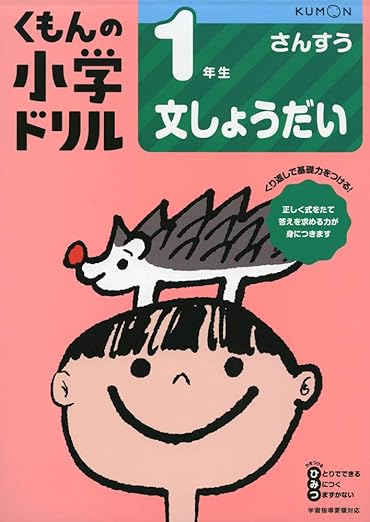
️ 学習用文房具
- コクヨの学習ノート: 昔ながらのノートが、今も根強い人気。文字練習に最適です。 ➡️ https://amzn.to/3GV2MVr
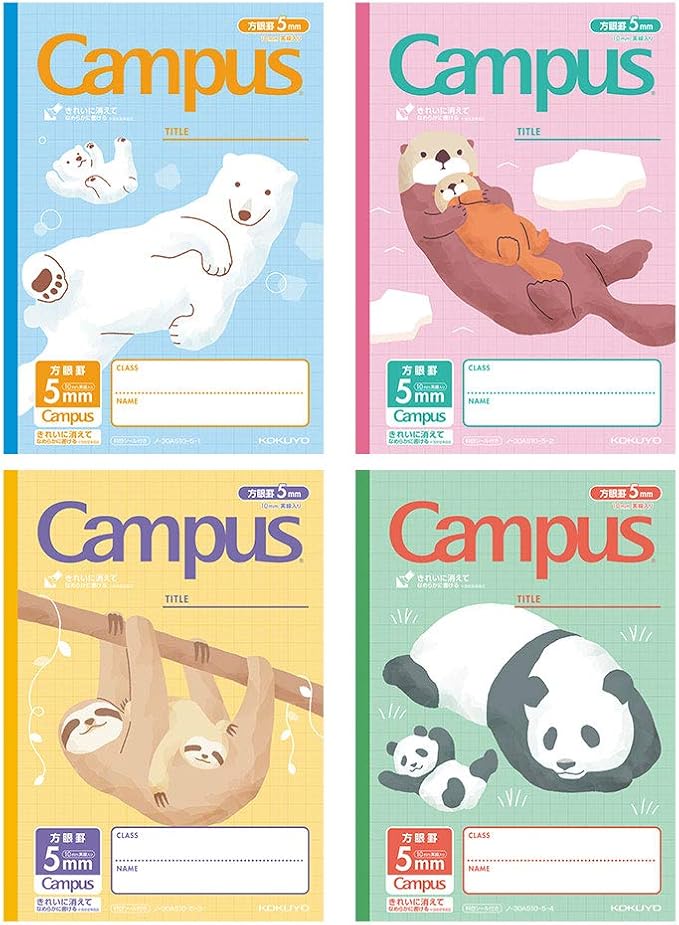
- パイロットのフリクションペン: 消せるボールペンで、ミスしても書き直せる安心感。 ➡️https://amzn.to/3S4E8nN
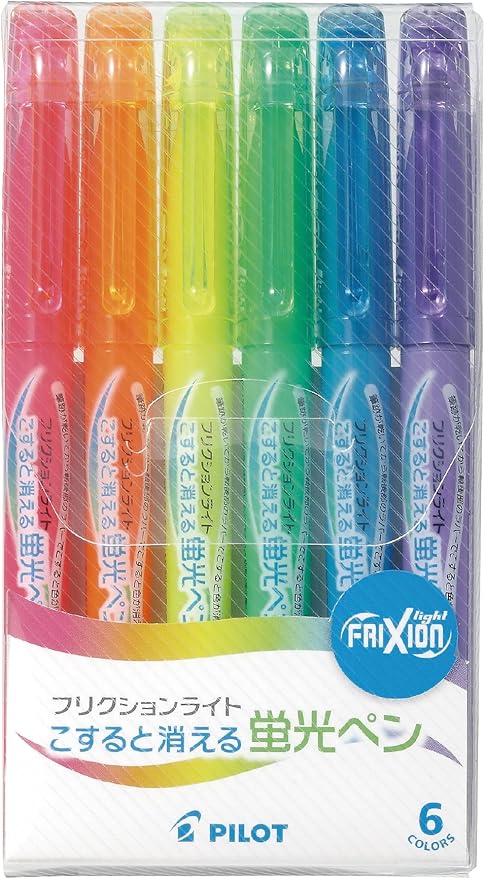
まとめ:小学校の歴史から学ぶこと
日本初の小学校が開校してから150年以上が経ちました。
教育は常に進化し続けていますが、根底にある「学びの大切さ」は変わりません。
現代の教育がどのようにして形作られてきたのか、そしてこれからどこへ向かうのか。
5月21日を機に、改めて考えてみませんか?
